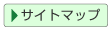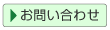リハビリテーション科
当院のリハビリテーション科についてご紹介します。
Rehabilitation
このページの目次
Ⅰ.リハビリテーションとは
病気やケガなど、何らかの原因で動くことが不自由になると、普段の生活のみならず、仕事や学校生活といった社会活動にまで不便が生じます。そのような状態からの回復を目指すのがリハビリテーションです。身体機能の強化や様々な動作の練習、日常生活動作(食事・トイレ・着替え・入浴など)練習、社会復帰を目指した練習など内容は多岐に渡ります。
「生活」は個人によって異なり、必要とされる活動も違います。当院では、それぞれの患者さんの生活背景を傾聴して目標設定を行い、自宅や施設生活復帰に向けたリハビリテーションを進めることを心がけています。
Ⅱ.リハビリテーション科について
当科は、理学療法(理学療法士5名)・作業療法(作業療法士3名)・言語聴覚療法(言語聴覚士1名)の3部門の総計9名からなります。さらに、訪問看護ステーションに理学療法士を1名配置し、訪問リハビリテーションを行っております。
病棟は、一般・地域包括ケアの2つがあり、両者で時期や全身状態に合わせリハビリテーションを行っております。
特色として、自宅や施設からの入院患者さんのみならず、他病院で入院や手術後のリハビリテーション目的の入院患者さんも多いことがあげられます。
必要に応じて、退院前に担当スタッフが自宅訪問を行い、福祉用具の導入や住宅改修の相談を行うなどの対応もしております。
カンファレンス(リハビリテーションスタッフ、患者本人、看護師、相談員、入退院支援室スタッフ、ケアマネージャー、家族、施設スタッフなどで集まり会議を行うこと)も積極的に行っており、施設との事前調査、入院中間・退院前などに実施しております。
令和7年5月より、土曜日や祝日にも一定の出勤体制を整え、リハビリテーション施行を開始します。
①理学療法部門紹介
理学療法部門では運動療法を通し、運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に治療を行います。そして、患者さんの身体機能の向上や社会生活に必要とされる動作の獲得を支援します。
また、当院では必要に応じてご自宅へ伺い、住宅改修の提案や福祉用具の紹介などを行うことで、患者様が安心して退院できるよう取り組んでおります。
②作業療法部門紹介
作業療法とは、日常生活の諸動作・家事・仕事・遊びなど人の生活全般に関わる活動を通して機能の回復や維持・改善を促す治療です。当院では日常生活に即した訓練や、調理・園芸などを取り入れています。退院に向けて必要な機能回復を促し、患者さんがいきいきとした生活に戻れるよう心がけています。
③言語聴覚療法部門紹介
言語聴覚部門では、脳血管障害や高齢による寝たきりでコミュニケーションや食事を摂ることが難しくなった方に対して、言語・嚥下機能の回復、維持を図る治療を行っています。当院では「最後まで口からご飯を食べる」をスローガンとし、各患者様に適した食形態の提案、飲み込みに関する筋力訓練、耳鼻科と連携して嚥下内視鏡検査を行い訓練にフィードバックするなど、生活に笑顔を取り戻すお手伝いができるよう心がけています。
④訪問看護リハビリテーション部門紹介
理学療法士が自宅を訪問し、実際の生活場面を見ながらリハビリテーションを行います。患者さん本人に対する治療のみならず、介護についての相談、自宅住環境の確認・福祉用具や改修提案などをさせて頂くことで自宅での生活の質の向上を目指します。
Ⅲ.リハビリテーションの対象疾患
当院の対象は、整形外科疾患に代表される「運動器疾患」、脳卒中に代表される「脳血管疾患」、入院中や自宅・施設生活中の安静等による体力や運動能力低下などに対する「廃用症候群」です。整形外科や内科や消化内器医師の指示の下でリハビリテーションを実施します。
①運動器リハビリテーション
手足・脊椎の骨折、腰痛、頸部痛、肩関節周囲炎、靭帯損傷、各変形性関節症、四肢の切断などが対象です。
②脳血管疾患等リハビリテーション
脳卒中、脊髄損傷、脳の外傷、中枢神経の変性疾患、小児発達障害などが対象です。手足や体や言葉の麻痺、嚥下機能麻痺、高次脳機能障害(注意や認識や判断や記憶や表出などの障害)、運動機能低下に対し実施します。
③廃用症候群リハビリテーション
入院中や自宅や施設生活中の安静等による、運動機能・呼吸機能・循環器機能・嚥下機能の低下などが対象です。
Ⅳ.リハビリテーション科からのメッセージ
リハビリテーション科では、住民の皆様が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるように地域で助け合える体制作りを支援し、地域に愛される病院となることを目標としております。自宅生活の方のみならず、介護施設生活中に廃用症候群などで各機能が落ちてしまった方々にもリハビリテーションを実施することで、地域住民の皆様が住み慣れた地域生活に復帰できるように努めてまいります。